第2回 強震動計算法
はじめに
耐震の入口の話として前回に引き続き、第2回は強震動の諸特性と計算法の紹介をします。
次回では最も破壊力ある地震動である断層近くの強震動の成因や作成法を説明し、強震動計算法を建物への設計用地震動の策定に活用する上での課題を述べたいと思います。
今回は強震動地震学という研究分野を含むため、少し難しい内容になるかもしれませんが、耐震設計を行う上での敵である強震動の正体を知ることは重要ですので、しばらくお付き合いください。
強震動の震源特性
【図1】に示すように強震動を計算するには、震源・伝播・サイト特性と呼ばれる地震動に与える諸特性を理解し、適切に評価することが必要です。
このうち伝播特性は震源から発生する実体波や表面波における減衰や散乱・分散などの諸特性を含み、サイト特性は観測点近くの地盤による地震動の増幅や継続時間の増大、卓越周期の発生、液状化に代表される地盤非線形などの多くの特性を含みます。
伝播・サイト特性を評価するには地盤構造モデルが必要になりますが、最近、全国での地盤構造モデルが整備されつつありますので、参照ください(例えば、地震ハザードステーションなど)。
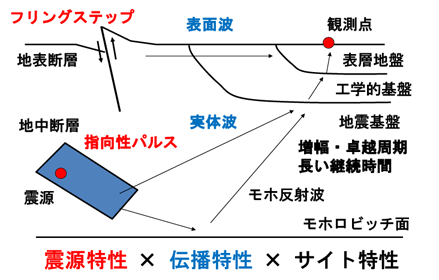
|
|
【図1】強震動評価手法における震源特性と伝播・サイト特性(グリーン関数)
|
|
伝播・サイト特性は比較的良く知られていますし、紙面の制約もありますので、ここでは次回に繋がる震源特性を中心として説明したいと思います。
まず断層震源のモデル化ですが、【図2】に示すような多くの震源パラメータで表現されます。
主なパラメータには、断層位置の長さ(L)・幅(W)、断層面の傾きである傾斜角(δ)、破壊の開始点(震源位置:X0 )とその伝播速度(Vr)、断層各点(ソース点:X )のすべり(D)とすべり角(λ)、などです。
震源層のせん断剛性(μ)に、断層面積とすべりを乗じた値(μDLW)は、地震モーメント(M0)と呼ばれ、震源の規模を表す重要なパラメータです。
現実の断層破壊は複雑な現象ですので、それを表現するために断層面を【図2】に示すように小断層に分割し、各小断層で断層パラメータを別々に設定します。
また断層面の中で特に強い地震動を生成する部分はアスペリティー、その他は背景領域、と呼ばれています。
次回に説明しますが、破壊力ある指向性パルスは、主にアスペリティーから発生しますので、この設定法は強震動計算をするうえで非常に重要となります。
震源パラメータの具体的な与え方は、対象となる震源断層と類似した過去の断層震源モデルのパラメータを準用する方法や、経験則に基づきアスペリティーや背景領域にて単純化されたパラメータを与える方法(強震動予測レシピ;地震調査研究推進本部、2008;日本建築学会、2009)、が提案されています。
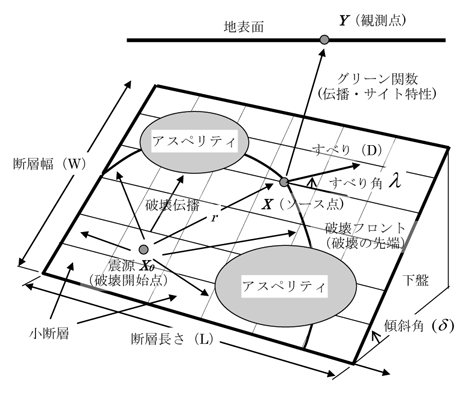
|
|
【図2】断層震源モデルと震源パラメータ
|
|
主な震源特性として、震源のスケーリング則や、放射特性、破壊伝播による指向性(指向性パルスなど)、地表断層によるすべり変形(フリングステップ)、などがあります。
放射特性や指向性パルスなどは次回説明しますので、ここでは震源のスケーリング則を紹介します。
これは強震動計算を行う上で小地震と大地震の強震動の大きさを規定する震源特性に関する重要な経験則です。
【図3】には震源のスケーリング則の模式図を示します。
図の曲線は震源スペクトルと呼ばれ、横軸は振動数(f)、縦軸は変位波形に相当する振幅スペクトルであり、振動数が0において、地震モーメント(M0)で基準化しています。
一般に震源スペクトルは低振動数ではM0にほぼ等しい一定値ですが、あるコーナー振動数(fc)より高い振動数では振動数の2乗に逆比例して振幅が減少します。
このモデルはω2モデル(オメガ・スクエア・モデル)、と呼ばれ、現在、強震動計算で最も広く用いられているモデルです(ここで、ωは円振動数)。
図には大地震と小地震の震源スペクトルがそれぞれ赤線と青線で示しており、また震源パラメータは、それぞれ上付きのLとSで与えています。
図中のNはスケーリングパラメータと呼ばれ、経験則により小地震と大地震の震源パラメータから(1)式で与えられます。
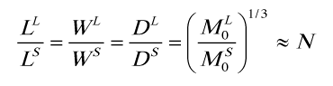
|
(1)
|
|
さて震源のスケーリング則とは、【図3】に示されるように大地震に対する小地震の震源スペクトルの比は、低振動数では地震モーメント(M0)の比であるNの3乗倍ですが、高振動数ではコーナー振動数(fc)が小地震の方が大地震よりも大きな値となるため、振幅比はN倍にしかならないという経験則です。
すなわち地震波形を比較した場合、変位では両者に大きな振幅の違いが出ますが、加速度にはあまり差が出ないことになります。
また小地震の地震動を観測して、これを大地震の強震動として用いる場合、この法則を用いて振幅の調整を行わないと経験上おかしな波形を作ることになります。
例えば、耐震設計では観測された地震記録の最大速度振幅を50cm/sなどで基準化して用いることがありますが、これでは【図3】の緑線に示されるように、一般には低振動数は過小に、高振動数は過大に評価してしまう可能性があります。
ω2モデルによる振幅補正は非常に簡単にできますので、関心のある方は参考文献などを参考ください(西川ほか、2008)。
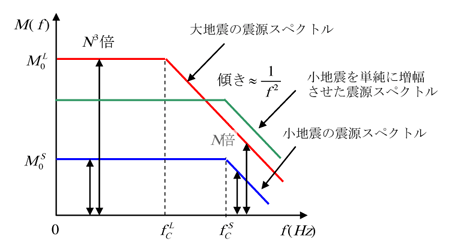
|
|
【図3】震源のスケーリング則(小地震と大地震の震源スペクトルの模式図)
|
|
強震動計算手法
次に強震動計算法を紹介します。
強震動評価法として最も汎用性があり、実用的なのは、(2)式による表示定理を用いる方法です。
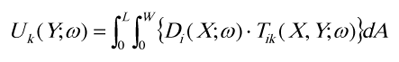
|
(2)
|
|
ここで、Uk(Y ; ω)は、観測点 Y、振動数ωにおける k 方向の変位です。
【図2】に示すように L,Wは断層面の長さと幅、Di(X ; ω)は断層面 X点における i 方向のすべり関数、
Tki(X ,Y ; ω)は X点から Y点までの波動伝播特性(グリーン関数)を表しています。
【図4】に示すように強震動計算では、ランダムな地震動特性が卓越する短周期領域では経験的・統計的手法を、一方、指向性パルスやフリングステップ、表面波などコヒーレントな特性が卓越する長周期領域では理論的手法を、それぞれ一般に使用します。
従って広い周期帯域の強震動は、前者の結果には長周期成分をカットし、後者には短周期成分をカットするフィルターを通して、両者を加え合せることで得られます。
このような手法はハイブリッド手法と呼ばれています。
両者の結果を接続するマッチング周期帯域は0.5から2秒程度ですが、一般に地震規模が大きくなると長周期側にずれる傾向があります。
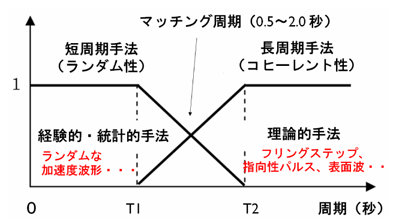
|
|
【図4】強震動評価における手法と対象周期(マッチング周期域T1-T2は通常、0.5-2秒程度)
|
|
経験的・統計的手法の代表例は、経験的グリーン関数法(半経験的手法)や統計的グリーン関数法です。
前者は実際に観測された小地震記録を用いて、大地震動を合成する手法であり、その際、小地震として【図2】に示す小断層を用い、震源のスケーリング則に基づいて大地震の強震動を合成します。
この方法は、想定される震源域で実際に小地震が発生し、かつ建設サイト近くで地震記録が得られている場合、最も効果的な方法です。
但し、実際にこのような理想的な記録が得られることはまれですので、人工的に小地震動を作成し、大地震動を合成する手法が開発され、統計的グリーン関数法と呼ばれています。
この方法は非常に簡単に強震動が作成できるため、広く用いられていますが、一般にグリーン関数は単純な直達S波ですし、震源のごく近傍では使用できない、など様々な制約があることに注意が必要です。
一方、理論的手法は(1)式をそのまま用います。
グリーン関数の選択により、平行成層地盤を対象とした理論手法(波数積分法など)と、盆地など不整形地盤を対象とした数値解析手法(差分法や有限要素法など)など用いられています。
前者は長周期だけでなく短周期まで高速かつ高精度な計算が可能ですが、対象地盤に制限があるため、一般に震源近傍の強震動評価などに適しています。
一方、後者は理論上では、どのような地盤にも対応可能ですが、計算時間やメモリー、地盤情報などの制約から長周期の強震動評価に適しています。
理論的手法や経験的・統計的手法は、それぞれの対象周期帯域で優れた手法ですが、両者を接続する際には注意が必要です。
すなわち一般に前者は乱数によるランダム位相を、後者は理論的なコヒーレント位相を用いていますので、そのまま単純に両者を重ねると一般に接続する振動数帯で振幅が小さくなってしまいます。
例として【図5】にω2モデルを用いた場合を紹介します。
【図5(a)】は単純なパルス状のすべり速度関数となるコヒーレント位相を与えた震源スペクトル、【図5(b)】はランダム位相を与えた震源スペクトルです。
図で赤線が実部、青線が虚部、太い緑線が絶対値を示します(震源スペクトルは【図3】に相当するものを1回微分しています)。
振幅の絶対値は両者とも同じω2モデルですが、(a) と(b)をそれぞれ低振動数と高振動数に使用し、これらを0.5 - 2Hzの振動数帯域で重ね合わせたハイブリッドとした震源スペクトルが【図5(c)】です。
図に示されるように接続振動数帯で振幅が大きく落ち込んでいます。
これは実部と虚部で正負の値が互いにキャンセルしてしまうためです。
従って、接続周期帯域ではできる限り両者とも類似な位相特性を持つ結果を用いて重ねる必要があります。
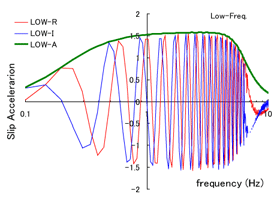
|
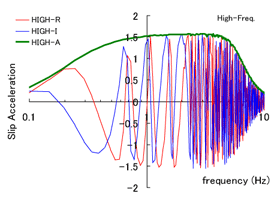
|
|
(a)コヒーレントな位相を与えたω2モデル
|
(b)ランダム位相を与えたω2モデル
|
|
|
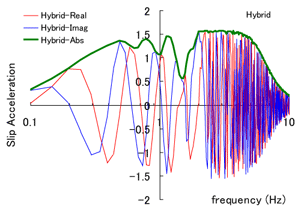
|
|
(c)両者で合成したハイブリッドなω2モデル(低振動数では(a)を、高振動数では(b)を使用)
|
|
|
|
【図5】ハイブリッド手法による接続震動数帯域(0.5 - 2Hz)での震源スペクトルの落ち込み
|
|
おわりに
今回は強震動地震学の成果である震源特性を中心に紹介しました。
少し難しい内容だったかもしれませんが、1995年阪神・淡路大震災の震源近傍の強震動や、2003年十勝沖地震の長周期地震動など、近年の地震災害では改めて耐震の入り口である強震動特性を理解する必要性が高まっています。
さらに勉強したいと思う読者は、参考文献をはじめ多くの文献がありますので、ぜひご参照ください。
次回は阪神・淡路大震災などで明らかになった震源近傍の強震動の成因やその策定法、さらに強震動計算した波形のばらつきや、設計用地震動への適用など、より具体的な事例を紹介したいと思います。
参考文献
- ■
-
西川孝夫 ・荒川利治 ・久田嘉章 ・曽田五月也 ・藤堂正喜 ・山村一繁、
建築の振動:応用編、6章 地震と地震動(久田分担)、pp.80-140、朝倉書店、2008
- ■
-
地震調査研究推進本部、震源断層を特定した地震の強震動予測手法(「レシピ」)、2008、
http://www.jishin.go.jp/main/kyoshindo/08apr_kego/recipe.pdf
- ■
-
日本建築学会、最新の地盤震動研究を活かした強震波形の作成法、2009
- ■
-
防災科学技術研究所、地震ハザードステーション J-SHIS、http://www.j-shis.bosai.go.jp/